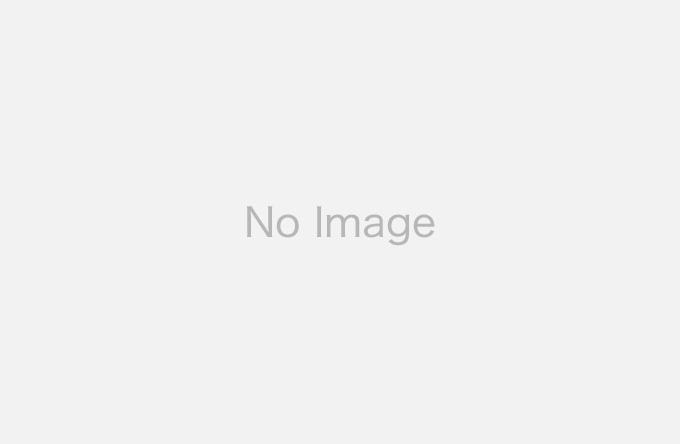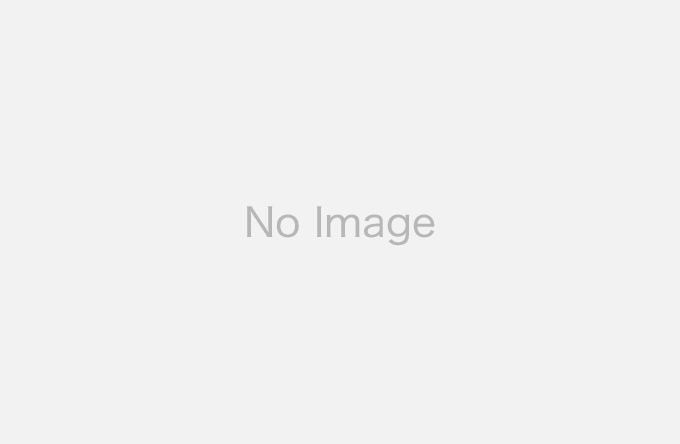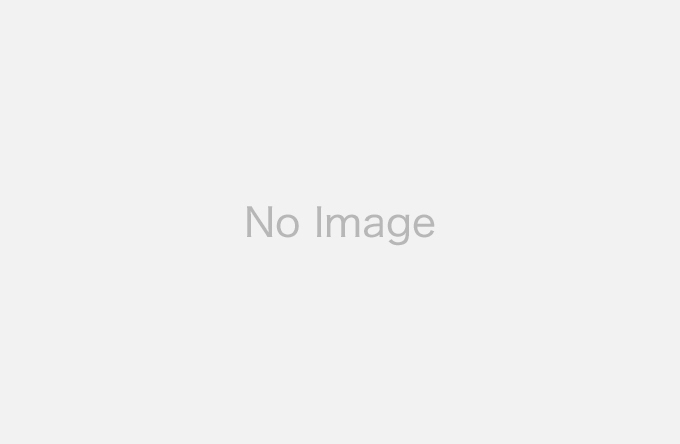.8 TENHACHI HOUSE CONCEPT
.8 TENHACHI HOUSE CONCEPT
新しい家のあり方とはどのようなものだろうか。
設計者の自邸であり、東京近郊にあるマンションの一室のリノベーション。67㎡のコンクリートで覆われた四角い空間の中で、家と生活についての思考を実現化した実験的プロジェクトである。
このプロジェクトでは、常識的な「家」に定義されている利便性から必要不可欠な要素のみを残し、また利便性とは異なる空間の豊かさを最大限に引き出すことを試みた。
この住まいのテーマは大きく2つ。
テーマ1:「余地」
場所や家具に、「ここは食事をするところ」、「ここは勉強するところ」といった役割を規定せず、自分で好きな場所を選択できる「余地」のある空間となるよう配慮した。
例えばこの家の中心には4.5mの大きなテーブルがある。
このテーブルでは、調理や食事、あるいは作業をする、キッチン、ダイニング、スタディースペースの領域が緩やかで、フレキシブルに使うことができる。
テーマ2:「つながり」
家とは、privateな行動と、publicな行動が入り交じる場所である。その2つの行動をつなぐ役割として、2つの大きな箱が配置された。2つの箱は、家の中にあるもう一つの家のようである。箱の中は、privateな領域で、箱は大きな開口部によって、外のpublicな空間と緩やかにつながっている。
白い箱は寝室であり、他の空間より床や空間の高さの差をつくることで、ねぐらのような囲まれた安心感のある場所となっている。開口部は、部屋の風の通り道を作っている。
木の箱は、浴室・洗面室であり、内部は白い空間となっている。バスタブやシャワーが舞台の主役であり、まるで立体的なフレームが奥の風景を切り取っているかのよう。通路に隣接しているフレームの面は出入り口が立ち上がり、空間を切り分け、一方でつなげている。
家の中の壁は、全て天井より低く、個々がオブジェクトとして独立し、形やサイズが不揃いである。床と壁のフローリングの目地を斜め45度方向に統一することで、不揃いなボリューム感が調和し、一体感を出している。







斜めに貼ったフローリング貼りの壁の中にはトイレが隠れている。無機質なコンクリートの質感が温かみのある木の素材感を引き立てる。

帰ってきて荷物をさっと置くことができるオープンクローゼット。なんでも気軽に置けるところがよい。

玄関は、既存の仕上げを剥がして、中古の足場板を壁に貼った。愛用の自転車を壁掛けし、アンティークショップで見つけてきた照明で演出をしている。
設計事務所
.8 一級建築士事務所
- 住所
- 〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋1-21-7-202
- TEL
- 090-9158-4470
- 代表者
- 佐々木 倫子, 佐藤 圭
- ご担当者様
- 佐々木 倫子 ,佐藤 圭
- URL
- http://www.ten-hachi.com/
- 写真提供
- ROOMBLOOM
建物概要
- 名称
- .8 HOUSE
- 所在地
- 神奈川県
- 施主
- S邸
- 設計 + 監理
- .8 一級建築士事務所
- 施工
- 株式会社 シームレス
- 工事期間
- 2014年9月~2014年12月
- 建築用途
- 住宅
ご採用商品

2024/01/09
千葉県 金谷の別荘
広葉樹と針葉樹がバランスよく織りなす自然あふれる山々を借景に、正面には金谷の海と大きな富士の山が望める高台という手つかずの別荘地との出会いから、このプロジェクトが始まった。
広大な自然の景色の中では多少の不便ささえも楽しめる、という遊び心ある施主のリクエストから、各室を分離した4棟建てで構成されたセカンドハウスが完成した。シンプルな外観はリゾートホテルのヴィラを彷彿とさせる佇まいとなった。
8帖のユニット空間を基本モジュールとして各棟を設計し、離れのような非日常感を演出。大きなテラスにプールを設えたメイン棟のLDKは26帖の吹き抜け大空間とすることで迫力のある借景を取り込む。
メイン棟と16帖のピロティを挟んで、プライベートな空間としてのゲストルーム棟は、大人がゆったりとくつろぐ場所としてホテルライクにデザインした。
絶景を余すことなく取り入れるよう、トイレ棟と浴室棟は建物のレベルを下げて眺望を確保している。
TIMBER YARDが提案する上質な素材を使用したオーダーメイドのオリジナルデザイン、国内外からセレクトされた一流の設備やインテリアが融合したラグジュアリーなセカンドハウスが完成した。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2023/12/01
東京都 まちと公園を纏う家
旗竿地における、周辺環境に接続する建ち方
計画地は都内有数の大きな公園を抜けた先にある、建蔽率40%、容積率80%の低密な住宅地。邸宅の生垣や庭木の緑豊かな景観が連続し、時折小さなカフェやギャラリーが入り混じる。自邸を計画していた私たち夫婦は、都内でありながら緑に恵まれ、ゆったりとした時間が流れる辺りの空気感を気に入り、まちと公園の気配を内から感じ取れるような住まいをつくりたいと考えた。
巡り合った土地は、北東向きの旗竿地。初めて計画地を訪れた際、長手方向に並列する隣地南庭の緑と、満開に咲き誇る寒梅が輝いていた。活用のし難さから敬遠されがちな敷地条件であるが、ゆったりとした周辺環境を活かす構成を採ることで、20mという敷地の奥行きも相乗し、敷地面積以上に広がりのある豊かな居住空間を獲得できると考えた。
公園側からのアプローチを迎え入れるよう、敷地の奥にL型のヴォリュームを配置。
生活に必要な機能を有する5層の矩形スラブを半階ずらしたスキップフロアとし、視線や光、風の抜けを確保した。
L型スキップフロアが囲む三角形のコモンスペース「さんかくコモン」は、ポーチ、ダイニング、ルーフテラスから成り、接道面に対し50度回転し斜めに構える東向き立面とした。接道面からの立面はBIMを用いて定点検証しスタディを進め、来訪者をかしこまらずに迎え入れる構えがこの旗竿地に建つ建築のふるまいとしてしっくりときた。今後、まちに「参画」する場として、小さな演奏会やマルシェなど友人知人が集う場に育てていきたい。
木製の大開口を通し、四季折々に変化する庭木の借景や朝陽を内部空間に取り込み、隣接する住宅との正対した見合いを避けている。
「さんかくコモン」が公と私の空間に介在する余白としてあることで、周辺環境との繋がりや光環境が異なる小さな居場所が5層の各所に生まれている。
コロナ禍を経て、働く、集うなど住まいの機能は以前より多様化した。時に応じ移り変わる使い方に合わせ、周辺環境を含む住まいの内外で最適な居場所を選択する毎日が、私たちはとても楽しい。
新築
戸建
トイレ
ナチュラル

2023/11/01
山梨県 F邸別荘
富士山を臨む大自然に佇むキャビン・ログハウス風の別荘を、木やメタル素材を使いながら、インダストリアルでモダンなインテリアへリノベーションした。既存の間取りでは10畳あった和室部分を6畳の小上がり畳スペースへ縮小し、拡張したLDKの一角には、庭や富士山が見える窓辺にワークスペースを設けた。外の景色を眺めながらのんびり料理を愉しめるように、キッチンのレイアウトを変更。奥まった場所にあった壁付けのキッチンを、対面式のL型へ造り替えた。また、モールテックスで仕上げ、重厚感のあるキッチンとした。ダイニング側のリビング収納は扉寸法を工夫して、アクセントウォールにもなるよう設計した。廊下からLDKにつながる建具をガラスにし、天井をひとつづきに見せることで抜け感を演出。前オーナーから引き継いだ暖炉は、使い込まれたアンティーク感とレンガの風合いが希望のインテリアに馴染みそうだったため、そのまま活かすことに。暖炉もまだまだ現役として使用でき、設備としても戦力となった。洗面台もキッチン同様モールテックス仕上げにし、シンプルでスタイリッシュな雰囲気に合うセラトレーディングの洗面器を選定。この別荘で施主は、リモートオフィスとして活用したり、週末は家族や犬とのんびり余暇を過す。暖炉に薪をくべたり、景色を眺めながらじっくりと低温調理に向き合ったり。都会の喧騒から離れ、ワイングラスを傾けながらゆっくり過ごす。スローライフを愉しむ大人たちの隠れ家だ。
リフォーム
戸建
洗面
その他

2023/10/02
栃木県 House in Tochigi
区画整理された郊外の住宅街の角地に建つこの住宅は、求められた床面積に対して敷地が十分にあった。
また、クライアントからの要望は唯一「重厚感があって、非日常を味わえる建物」にして欲しいとのことだった。
まず、敷地の大きさを考え、建築と庭が一対の関係である『庭付きの住宅』とは違い、建築や外構と、敷地の余白の関係性が豊かになる住宅にしようと考えた。
そこで建物は、部屋の特性や近隣との見合いを考慮して配置を始めた。建物の輪郭が生まれると同時に浮かび上がってくる余白のスペースと豊かな関係を築けるよう綱引きをし、変則的なH型平面に着地した。
そこで生まれた大小さまざまなスペースが庭となり、それぞれ違う性格が与えられた。
また、要望にあった「重厚感」や「非日常」に対しては、どっしりと構えた中に、どこか歪められた設えを用いたいと考えた。
例えば、庭の大きな円弧のアプローチを歩いて行った先にある、高さ3mを超える玄関扉、暗いホールの先にある階段の上から、陽の光が燦燦と降り注ぐトップライトなど。
重さや軽さ、住宅のスケールや明暗に、歪みや強弱を与えるような仕掛けを散りばめた。
この住宅は、性格の違った庭や周辺の山々の景色を存分に取り込み、部屋を移動するたびに別世界のごとく感じ、それと同時に存在する、少し歪められた非日常の設えの連続が、新たな日常へと誘ってくれる。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2023/08/01
愛知県 社が丘の家
自宅兼事務所。間口が狭く、3方は建物に囲まれている細長い敷地だが、東には66haの広い緑地を望む美しい場所であった。当時残っていた旧宅の2Fから見た緑いっぱいの風景が忘れられず、この土地に家を建てる計画を始めた。敷地には何度も足を運び、同時に東に広がる森への探検も幾度となく行ううち、この森に続くようなアプローチを持つプランにしたいと考えるようになった。周辺環境に配慮した控えめな佇まいと、朽ちても美しい外套をまとった建物を作りたいという思いは、常に心に留めているテーマである。そこには日本人が太古より、いびつさ、不揃いであること、そして何より寂びに美を感じていたことを思い出させたいという願いがある。パートナーが作る地元の土を使ったタイル、コンクリート、国産スギのサッシ、木毛セメント板が、この外観の要素となった。長くインテリアデザインの仕事に従事しており、素材の質感や厚み、色、重さといった視覚や触覚から得られる要素には常にこだわりを持ってきた。水栓金物やシンクといった器具に至っては、その機能美や技術の高さも見ることになる。薄いリムのSCARABEO社のTR2シリーズの洗面ボウル、水栓金物は細部まで妥協のないデザインのKWC社のAVAシリーズ、キッチンにも同社の水栓金具を採用。2Fのトイレは、円形で大きさもちょうど良いものと思い選んだ手洗器が偶然にもSCARABEO社であった。ここでの生活を始めて2度目の夏を迎えた。敢えてコンクリートを打たず、転圧とした駐車場のタイルの間に苔が生え始めた。いつかこの敷地内の植生が森と繋がり、この景色の一部になっていけば良いと願っている。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2023/06/01
静岡県 森を育む丘の家
静岡県某所の区画整理事業地の一角に、丘のような住宅を設計した。
森を切り拓いて作られた敷地周辺には、設計当初街路樹や公園などの緑は一切なく、 没個性の人工的な風景が広がっていた。新興街区に建ち始めた建築は配置も高さもバラバラでとりとめがなく、町並みとして目指す方向が定まっていないように見えた。私達はこの場所に、町の成長や豊かさに寄与するような、そんな風景を作りたいと考えた。
住まい手は、人間と犬が垣根なく快適に共存できるように、「外部のように開放的な内部空間」や「内部のように落ち着く外部空間」を求めていた。
まず敷地の高低差を利用して丘状の地盤を設計し、地盤内に内外部空間を混在させることで、屋内と屋外の境界を曖昧にした。
つぎに敷地の気候環境を丁寧に検証することで、空調システムに頼らなくても快適で、四季の移ろいを愛おしみながら生活できるように設計した。
敷地境界を塀で囲わずに緩やかに繋げたことで、住宅内から眺める空はどこまでも続き、道往く人々は豊かな緑を享受することができる。
この丘のような建築は大地のように力強く存続し、長い年月をかけて木々を育む。木々が成長すると丘は小さな森になり、この街のひとつの拠り所として愛され続けていくことに期待している。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2023/04/03
長野県 矢ケ崎N邸
軽井沢東部の山の稜線に建つ別荘である。豊かな森のなかでゆったり過ごしたいとのクライアントからの要望に応えた。
周囲の木々に溶け込ませるため、建築の高さを低く抑えた木造の小屋を分散して配置している。
各所に中庭が生まれ、様々な空間が森の中に埋め込まれたように見え隠れし、どこにいても自然を感じとることができる。
リビングダイニングのダイナミックな無柱空間が暮らしの中心となる。
空間の主役となるベイマツ無垢材の端部は手ばつり加工が施されており、手仕事の温かみが感じられる。
内壁の仕上げは古材と漆喰塗りでまとめている。自然に晒されてきた板材が外部の樹木の幹の色味とも見事に調和しており、役目を終えた柱梁材がアクセントとなり全体を引き締めている。
四方に設けられた開口部を通して自然との一体感を生み出し、間接照明で照らしあげられた空間がやさしく包み込んでくれる。
室内装飾の照明器具や家具にも自然の草木のアレンジを積極的に取り入れることで、自然材料のやすらぎと手仕事の安心感を身近に感じられる。
木のもつ魅力に満ち溢れた別荘が、森のなかに結実している。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2023/03/01
岡山県 Barn Find House
岡山県津山市にある、緑あふれる山の中腹にある白い平屋は、ご夫婦が自然豊かな環境を求めて建てた住まいだ。ご主人はバイクが置けるガレージのある平屋を、奥様は旅で集めたアイテムが置ける空間を希望。欧米では納屋で長く眠っていた希少品を「Barn find」と呼ぶ。その物語になぞらえてコンセプトを“Barn find House”とし、ご夫婦が好きなもの、思い入れのある物を詰めこみ、愛でることが出来る空間を提案した。建物は切妻屋根の木造の平家を2つ並べ廊下で繋いだ。西側の建物にはエントランスと水まわり、リビングダイニングキッチンを。東側の建物には寝室を配置。扉の数を最小限とし、平屋ならではの移動を楽しめるようにした。白を基調とした内装は、ご夫婦のお気に入りのものが映えるギャラリーのような空間となった。リビングとダイニングの間に暖炉を設置し、どちらからでも炎が見られるうえ、暖炉に火をつけていない時はアート本やオブジェを並べられるよう十分な奥行きをとっている。廊下や水まわりはフラットな天井の仕上げに対し、寝室やダイニングキッチンは小屋組みの高い天井に。天井高や床のレベル差によって空間にめりはりをつけるようにし、2つの建物をつなぐ廊下の両サイドには、天井近くまでの大きな窓を設けた。起床時は朝日を浴びて、夜は月明かりを見ながら眠りに誘われる。空間を移動することでムードが変わる楽しさを味わうことができる。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2023/01/10
東京都 AO house
ビルのオーナー住戸部分を両親から子世帯が受け継ぎ、子育て世代のライフスタイルに合わせた全面リノベーション。
間取りはリノベーション前と同じ3LDK。ご実家でもあり、これまで住んでいて不便に感じていたことや有効利用できていない部分を見直し、各部屋の面積配分や動線を修正していった。
リビングダイニングは、家族が集いやすいように、できるだけ広いスペースを確保し、その窓際に家族共有の書斎コーナーを併設した。
キッチンは、食材の搬出入をしやすいように玄関とダイニングからの動線に配慮した。また、家事をしながら子供の勉強を見ることができるように、ダイニング側のカウンターを広くして、家族が集まりやすいダイニングキッチンとなるように計画をした。
オープンキッチンからダイニング、リビングへと一室空間となるため、キッチンとカウンター収納などの造作家具は統一したデザインとなるよう、置き家具も色のトーンを合わせてコーディネートしている。ダイニングテーブルは色味や大きさがなかなか合うものがなく、今回のプロジェクトのためにデザイン製作をした。
洗面スペースは、個室とはせず廊下の一角に設けることで、複数人で同時に手洗いや身だしなみを整えることができるようになった。
トイレにはしっかりと手洗いができるように、大きめでフォルムにデザインが感じられる手洗いボウルを設置した。
リフォーム
マンション
洗面
アーバン

2022/12/01
神奈川県 葉山の住宅
神奈川県葉山町、閑静な住宅地に建つ新築の戸建住宅。
葉山を新たな住まいに定めたクライアントご夫妻は、この地の空気感に合う、おおらかな暮らしのイメージとして、吹抜けのある住空間を希望された。
1階には家族のつながりが感じられる、LDKからなる一体の空間、2階には個室を配置し、そこへ空間の広がりを獲得するようテラスを各階に加えた構成とした。延床面積を30坪ほどに抑えながら、各階に設けた2つのテラスは、内部空間に対し、それぞれ異なるかたちで外部への広がりを見せている。
1階リビングの南側にあるテラスは、内部床が外部へ引き出されたようなスペース。建築の操作としては、2層吹抜けの袖壁を外部へ伸ばしつつ、前面の道路側にアイストップとなるコンクリート壁を立てることで適度に視線を遮り、外リビングのような領域とした。
2階のテラスは、南北に細長い屋根・壁のあるトンネル状のテラス空間を建築内部に引込むように設けている。室内からは、この空間は外部でありながら屋内のようにも視認され、隣接する空間に奥行きを与えている。屋内のような居心地を感じられるこの半外部空間は、ハンモックでくつろぐなど葉山町の光や風を日々の暮らしの中で楽しむ場所にもなっている。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2022/11/01
兵庫県 新在家の家
中庭を中心として南に平屋、北に2階建ての棟がある。2つの棟は渡り廊下でつながっており、平面図で見るとH型になっている。
道路に面している平屋の棟にはコンクリート打ち放しの塀を設け、中庭は平屋の棟によって、プライバシーが確保されている。
平屋と2階建ての棟をつなぐ渡り廊下は、中庭を2つに分かち、それぞれ趣の異なる外部空間としている。一つはリビングに面しており、季節の移り変わりを感じられる庭、もう一つはプライバシー性の高い活動的な庭となっている。
リビングの奥にはスケルトンの階段がある。
その上部のコーナーにトップライトがあり、北側の空間に明るさをもたらす。
新築
戸建
キッチン
ナチュラル

2022/10/03
長野県 FOREST BASKET
軽井沢の手つかずの雑木林が残る別荘地に建つ、都心から離れて家族でゆっくりと過ごせる週末住宅。
森の木々から光と風を包み込むように、高さ6mの天井から三角形の深い庇が伸びてテラスを覆う。
庭とテラスに面するガラスの一面大開口を背にして、中央に位置するストーブから放射状に、それぞれオープンキッチン、ダイニング、リビングを構成。
リビングのソファは床より45cm下げることで、落ち着きのあるカンバセーションピットとなっている。
また、オーナーからの要望でテラスの一部は網戸で囲えるようにし、虫などに悩まされることなく屋外で過ごせる工夫をした。
奇しくも竣工後すぐにワーケーションで長期滞在することになり、食事の場所としても仕事場としてもこの屋外空間を、大変気に入られたようだ。
セラトレーディングは海外輸入衛生機器の代理店として長い歴史と実績があるため、品質含めて安心感がある。
実際に、20年前に取り付けた廃番となった商品の不具合にも、資料を探してくれたり親身に対応してくれた。
新築
戸建
浴室
ナチュラル

2022/09/01
東京都 h37s
東京・目黒区にある築20年のマンションの一室に、猫2匹と暮らす50代のSさん。ご自身で薬膳料理を作ったり、器を集めたり、遠方まで気になる照明器具や家具を見に行ったりと、「食」を中心に、丁寧で豊かな生活を楽しんでいる。今回のリノベーションでは、将来、自宅で料理教室を開くために「調理のデモンストレーションもできる大きなキッチン」がテーマに。
リノベーション前の間取りは62㎡・2LDK。細切れになった個室とそれらをつなぐ廊下で構成され、有効に利用できていないスペースや倉庫と化した部屋など、広がりや繋がりを感じにくい間取りだった。それらを刷新し必要なスペースを再構築する上で、既存のパイプスペースや配管上の制約から大きく移動できない水まわりを住戸の一方に寄せ、残りは廊下のない大きな1LDK空間とした。これまで間仕切壁で切れ切れになっていた連続窓が一堂に会されたことで、外部への視覚的な広がりも得られるようになった。
空間を広くとるため既存の天井は解体。コンクリート打放しを生かし、床はコンクリートのようなテクスチャーの大判タイル、壁は木の繊維をセメント成分で固めた木毛セメント板の仕上げとした。グレー系のハードな質感に対して、家具や間仕切り壁の木の質感をバランス良く配置することで、上質で飽きのこない大人のリノベーションを実現。
料理教室のための大きなキッチンカウンターは、玄関の正面に配置しパブリック性を持たせ、家の顔となるべく、ekreaのオーダーキッチンで存在感のあるデザインに。キッチンにも、収納家具や間仕切り壁と同じ框フレームやラタン張りのディテールを採用することで、空間に全体的な統一感を持たせている。
リフォーム
マンション
洗面
ナチュラル

2022/08/01
東京都 豊島区南長崎project
以前建築家のイベントで出会った奥様から届いた一通のメールで始まったプロジェクト。
現在のお住まいとは別の場所に新築することも選択肢にあったが、ご家族で現在の場所での建て替えを決意され、ご相談を受けた。
家族は50代のご夫婦と成人されているお子様2人に2匹の犬で構成される愛犬家のご家族。
ご主人は費用面、奥様はデザイン面とそれぞれはっきり役割分担され、奥様のこだわりを実現するプロジェクトが始まった。
条件は「楽しい暮らし」と「愛犬にも優しい住まい」、イメージはクラシカルモダン。
愛犬のための床材選びも重要事項であった。
間口が狭く、奥行きが深い敷地。
必要な居室は、LDK、主寝室、子供部屋2室、ご夫妻のお母様が使われる寝室、ご主人の書斎。ここに水まわりを加えると、敷地に対して部屋数が多かった。
建築基準における高さと仕様の制限があるなか、ご要望のイメージや暮らし方などのこだわりを叶える方法を検討した結果、スキップフロアが最適であると判断した。
スキップフロアは、1つの階層に複数の高さのフロアを設けるので、生活していくなかで頻繁に上り下りが生じ、住まわれる方の負荷が大きい。また、設計が複雑になり、工事費もUPするため、これまで積極的に採用しなかった手法であった。
しかし、今回のプロジェクトにおいては、部屋数を確保しながら、開放的に空間を使うことができ、さらに奥様のこだわりとご要望を実現できると考え、採用した。
仲が良い家族と愛犬の団らんの時間と、プライベートな時間のメリハリを演出したことで、より豊かな暮らしを楽しむことができるようになった。
新築
戸建
洗面
アーバン

2022/04/01
東京都 染織りの家
東京・西荻窪、骨董通りを抜けた住宅街に建つ、木造3階建ての家。1階は染織作家である妻・高見由香氏のアトリエ、2・3階は3人家族のお住まい。20坪と限られた敷地だが、車を持たない分、アプローチに緑ゆたかな庭をとることが出来た。アプローチを彩る四季折々の植栽は、家族が楽しめるだけでなく、道行く人々を和ませてくれる。1階は創作のアトリエと、展示会のギャラリーを兼ねており、靴のまま入れる広い土間空間に。通りに面しても、1・2階を貫く大きな窓を設けている。周りは2階建ての建物が多い住宅街のため、家族で過ごすLDKを見晴らしのよい3階に上げて、天井を高くとった開放的な空間に仕上げた。2階は、寝室や水まわりのプライベート空間。1階と3階を「美しく、居心地のよい空間」として最大限生かせるよう、挟まれる2階は天井高を抑え、コンパクトで使い勝手のよい家事動線を目指した。セラトレーディングの商品は、プロダクトデザイナーである夫とともに、夫妻で吟味し選定した。
新築
戸建
洗面
ナチュラル

2022/03/01
沖縄県 BLUE STEAK WONDER CHATAN(沖縄北谷)
2020年12月24日開業の『BLUE STEAK WONDER CHATAN(沖縄北谷)』は、海を見ながら暮らすように滞在するというコンセプトのもと、どこか異国を訪れているような、旅の情緒感を大切にした唯一無二の存在感を持つホテル。
世界・日本各地を旅した沖縄県在住画家の梅原龍氏が監修。
~ゲストに提供しているものは「寝るためのベッド」ではなく、「かけがえのない旅」そのもの~
ゲストが旅の仲間(大切な家族や友人など)と暖かな団欒をし、『また、ここに来たいね』という思いを持ち帰ることができるような、豊かな時間を過ごす居心地の良い宿を想像して造り上げている。
優しく手と心に馴染むオーダーメイド家具
家族や友人同士で時間を忘れて団欒できるリビングダイニング
どの時間に見ても美しい自然光を採り入れるガラスブロック(明け方、直射日光、晴れの日、雨の日、月明かり・・・)
日常の境界をなくす使い勝手の良いキッチンは、海を見ながら料理が出来るホテルの共通コンセプト
すっきりして表情のある壁と天井
目に映る風景と景色・インテリアの魅せ方を設計し、ナチュラルな空間で、落ち着いた雰囲気を作っている。カーテンや照明、家電から食器に至る全てをコーディネートすることで、快適で感性に訴えかけるデザインとなっている。どこにいても居心地が良く、『ずっとここに居たい』と思える客室。
白で統一した開放感のあるバスルームには、セラトレーディングのペデスタルタイプの洗面ボウルを採用。デザインが完結しており、一体型のカウンターには物を置くこともできる。
リフォーム
ホテル
洗面
シンプル

2022/02/01
東京都 KAI house
子供たちが独立後、お母様が一人で住んでいた住居に再び子世帯家族が一緒に暮らすことになり、ビルのワンフロアを二世帯住宅へリノベーションした計画。
既存の間取りはいわゆるnLDK型のプランで、個室ごとにRC造の躯体で覆われており、生活の変化に対応しにくい構造だった。これから再び共に暮らす家族がプライバシーを保つ場所を確保しつつ、お互いの気配を感じられるような住まいの在り方を考えた結果、刷新した空間にアップデートするのではなく、家族の成長に応じて思い出をつなぎながら、住み継がれていく住まいとなるよう痕跡を残してデザインを再構築した。
例えば、今は亡きお父様が新築当時に要望した広々としたホールや幅広の廊下は、各空間と家族をつなぐターミナルとして回遊させ、使い方や状況によって各部屋と一体になったり、個別にしたりと使い分けができるようにした。新築当時の思い出が残るステンドグラスの窓下には子供が遊べるベンチコーナー、そこに面して書斎スペース、その様子をリビングから望むなど各居場所が緩やかに連続し、共に暮らす家族の関係性や空間の多様性を包括するおおらかな空間となった。
親世代から子世代、また次の世代へ。今後も家族の成長に応じて住まいとしての環境の変化を期待している。
リフォーム
戸建
洗面
ナチュラル

2022/01/05
富山県 消滅集落のオーベルジュ「Cuisine régionale L’évo」
人口わずか500人の富山県南砺市利賀村に、かつて存在した集落である「田之島」。一度は消滅したこの集落を、まるごとホスピタリティの空間としてデザインした、究極の地産地消を目指したオーベルジュ。地域に根差した文化や建築様式を読み取りデザインすることで、この場所ならではの新しい風景をつくった。
素材を大切にするこの施設では、食材はもちろん、水にまでこだわっている。周辺の山間から集められた澤水によって活動が成り立つこの施設において、衛生器具は、ここでの体験を演出する重要な役割を担う。土着的な建築デザインの趣に馴染みながらも、ラグジュアリーな宿泊空間を演出できる器具を模索する中で、洗練されたフォルムのグレー色の陶器に辿り着いた。施設の空間を象徴するデザインのひとつとなった。
リフォーム
ホテル
洗面

2021/12/01
福岡県 東峰村 古民家ヴィラ「あんたげ」
福岡県東峰村で2018年に開催されたこのコンペは、古民家を宿泊施設にリノベーションし、高齢化による農地(棚田)や景観の保全をしながら、竹地区に新しい仕事を創出しようという試みであった。
東峰村・竹地区の棚田は、日本棚田100選に選ばれる風光明媚なところ。既存の古民家は、その棚田の中で増改築を繰り返していた。我々は、この古民家を本来の姿に戻し、床のおおよそ1/3にあたる部分に、上下の棚田を繋ぐ土間空間を挿入することを提案した。
土間空間は既存の天井を抜き、梁レベルにロの字型の水平補強を施し、古民家が本来内包している小屋裏空間を大きな吹き抜け空間として表出させた。
古民家特有の勾配屋根のもと、利用者は太く大きな丸太梁が飛び交うダイナミックな空間に包まれる。土間空間の南北の壁は、内部からも石垣が見えるよう開放し、棚田の中にいることを身体で感じることができるようにした。
土間には大きなキッチンを置き、宿泊者はもちろん、宿泊者以外の人も料理教室や食事会などのイベントに参加ができる。
この土間空間を挟んで、棚田側には八女長野石を使った浴室などの水まわり空間、道路側には既存の古民家の部屋割りを利用して、和室と寝室を計画した。
どこにいても棚田を感じられるこの建築に対し、上品にさりげなく必要な機能を叶えてくれる、セラトレーディングの製品を採用した。
リフォーム
ホテル
洗面
和モダン

2021/11/01
東京都 House with 5 exterior spaces
敷地は商店街に面する角地。周辺には3階建てが建ち並ぶ環境の中、どのように外部からの視線を遮断し、内部からの景色を獲得するか・・・そのことを常に考えながら、何度もプランを練り直した。
限られた敷地を最大限に活かした広がりの感じられる家、エレベーターや全館空調システムを導入したいというお施主様のご要望もあり、断面設計は緻密に計画した。外部空間を縦横に取り入れ、天井高と窓の関係性を工夫したことで、体感として広がりのある空間を創ることができた。
外部空間は浴室の前、キッチンの横、くつろぎの間の横、ペントハウスから出られる大小2つの屋上空間が5つあり、この外部空間がこの家に豊かさをもたらし、また、この家を形作るコンセプトになっている。
お施主様との対話を重ねる中で、この家にはセラトレーディングの商品が一番良いと思い、ショールームにお連れしたところ、質感もデザインも気に入り、採用となった。
新築
戸建
洗面
アーバン